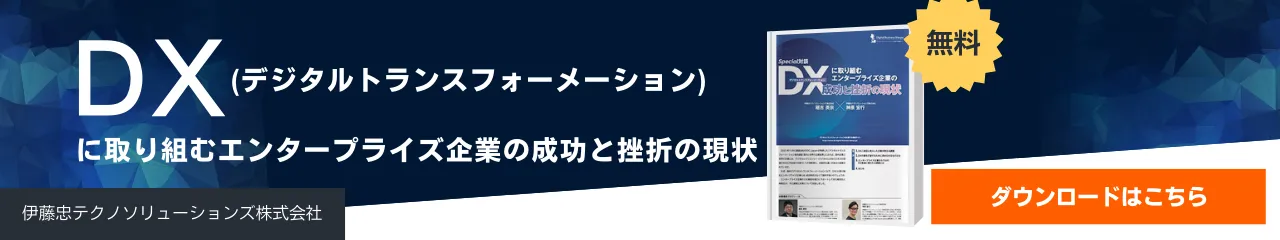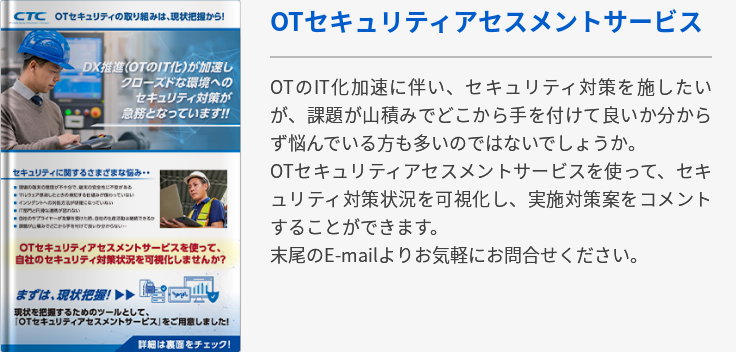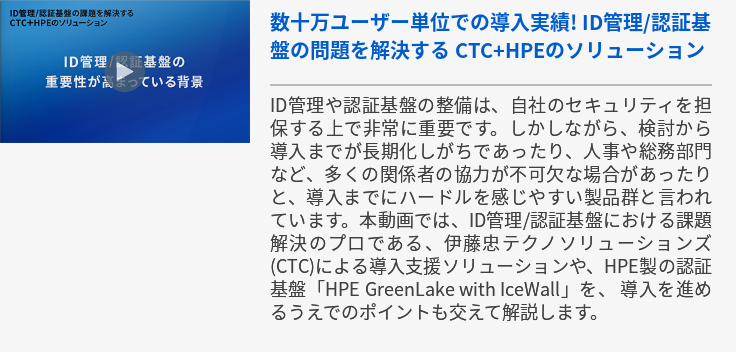ID管理の複雑化は、多くの企業が直面する重要な課題です。ハイブリッド環境におけるセキュリティリスクを回避するには、現在の運用状況の可視化や統制の強化、自動化に向けた取り組みが有効です。本記事では、ID管理における代表的な課題やリスクと解決策、アセスメントを活用して現状を明確化する方法を解説します。

自社のID管理課題を正確に把握できているか?可視化の重要性

多くの企業がID管理における課題を既知のものと認識し、継続的な対策を講じています。しかし実際には、煩雑化するID管理に対応しきれていないケースが少なくありません。エクスジェン・ネットワークス社の調査では、ID・アカウント管理の運用において、大企業の約45%が「管理の複雑化」を自社の課題と回答しており、潜在的なリスクへの対応不足を懸念しています。
こうした課題を解消するには、まず自社の直面している問題を正確に把握し、適切に対処することが重要です。現状の課題を正しく把握し、体系的に整理することが、組織全体の統制強化と自動化を成功に導く重要な起点となります。
参照元:エクスジェン・ネットワークス「ID管理の課題と取り組みたいことTOP3 ~数字で見るID管理2023」
ID管理における代表的な課題7つ

企業規模が大きくなるほどID管理は複雑になります。セキュリティリスクや運用負荷の増大だけでなく、コンプライアンス遵守における深刻な問題も引き起こしかねません。
退職者・異動者のアカウントが残存したまま放置されている
異動や退職が集中する年度末は、不要なアカウントの削除漏れが起きやすいタイミングです。業務システムやクラウドサービスに不要なアカウントが残っていると、使われるはずのないIDが有効なままになり、不正利用や情報漏洩につながるリスクがあります。
Kaspersky社の調査によると、日本企業の約34%が退職者に対するアクセス制限の実施が不十分であると回答しています。このようなリスクの回避に向けて、定期的なIDの棚卸しや削除の確認を徹底することが求められます。
参照元:Kaspersky「<Kasperskyレポート:企業内のデータ管理に関するグローバル意識調査-2>従業員の3分の1が、退職後も以前の職場の共有ファイルなどにアクセスできると回答」
手作業によるID管理が属人化を招き、運用が非効率化している
Excelなどの手動管理が常態化していると、ID管理を担当する人に業務が集中しやすく、作業負担も大きくなります。棚卸の結果が管理台帳に反映されない、設定変更が漏れるといったミスオペレーションも起こりやすく、実際の運用とのズレを招く原因にもなりかねません。
手作業に依存したID管理は、属人化やミスの要因となるだけでなく、組織全体の生産性にも悪影響を及ぼすおそれがあります。このようなリスクを回避するためにも、属人化を解消し、標準化された管理体制を構築することが重要です。
過剰な権限付与(オーバープロビジョニング)が常態化している
業務に必要のないシステム権限が付与されるオーバープロビジョニングが常態化していると、誰がどのシステムに対して権限を持っているのか、正しく把握できません。万が一、過剰なアクセス権限を持つアカウントがマルウェアに感染した場合、被害が拡大するリスクは高くなります。
従来のID管理は入社時の手続きに偏りがちで、異動や退職時に権限の見直しが行われず、不要なアクセス権限が残ったままになるケースが少なくありませんでした。また、社員以外のユーザーへ対応する際は手作業に頼ることが多いため、権限の棚卸や監査対応の際に多くの時間と手間を要します。複雑化した権限管理は、統制を図る上で大きな障害となっており、多くの企業がこの課題に直面しています。
ID・権限管理ルールが明文化されていない、または形骸化している
誰が、いつ、どのような条件でアカウントの発行や削除を行うのか、運用基準を明確にする必要があります。権限付与の基準が不明確な状態は、内部の情報漏洩や不正に繋がりかねません。
NTTコム リサーチにより、従業員規模が100人以上の企業を対象に行われた調査では、IDやパスワード管理について「社内でルールが明文化されている」との回答は約50%にとどまりました。また、情報セキュリティに関しては「ルールが文書化されておらず、個人の判断に任されている」という回答が30%を超えています。
そもそもルールが明文化されていない状態では、適切な運用や統制が成り立たず、リスクの温床となりかねません。また、ルールがあっても現場に浸透していなければ、実態との乖離は広がる一方です。こうした課題を解消するには、社内で共通認識を持つための仕組みづくりが欠かせません。
参照元:NTTコム リサーチ「企業の情報セキュリティに関する調査結果」
システムごとにID管理が分断され、全体像が見えない
各部門が業務のニーズに合わせて個別にSaaSを導入した結果、ID管理が分散し、全体の利用状況を把握しづらくなるのはよくある課題です。
たとえSSO(シングルサインオン)やIDaaSを導入していても、連携されていないシステムが多いと、IDの一元管理は実現できません。このような管理の二重化と煩雑さが、権限付与のミスや不要アカウントの削除漏れを引き起こし、セキュリティリスクの増大へとつながります。
また、棚卸や監査の場面では、システムごとに個別の対応が必要となるため、業務の非効率を招きます。近年、SaaSの利用が拡大する中で、統一的なID管理の仕組みが強く求められているものの、対応の範囲や優先度の判断が難しく、着手できていないケースも少なくありません。セキュリティやガバナンスの観点からも、早急な対策が必要です。
ログ取得やアクセス履歴の管理が不十分で監査に耐えられない
「いつ、誰が、何にアクセスしたか」というログが不足していると、不正アクセスが発生した際に被害の拡大を防げず、対応が後手に回る恐れがあります。
情報漏洩の経路や関与した人のIDを特定するために、多くの手間が必要となれば、監査対応は効率よく進められません。例えば、PCI DSSでは監査ログを最低1年保存することが求められ、直近3カ月分については迅速に分析できる状態での保持が義務付けられています。また、日本セキュリティ監査協会(JASA)でも、監査ログを1年以上保存することを推奨しています。
さらに、ログの改竄防止や暗号化、別のサーバへ保管する仕組みが整備されていないケースも多く、ログ管理の運用体制全体に課題が残されているケースも少なくありません。運用の属人化を解消するための仕組みづくりとして、組織全体でログ管理の基盤を強化し、運用の標準化を進めることが大切です。
オンプレミスとクラウドでID管理が分断され、統制が取れない
ハイブリッド環境におけるID管理の煩雑化も、見過ごせない課題のひとつです。オンプレミスとクラウド、それぞれの環境でID情報を個別に管理していると、同期が取れず、利用状況の把握や制御が難しくなります。
また、複数の管理ツールや認証方式が混在することで、組織全体の可視化や統制も困難になり、セキュリティや監査対応に影響を及ぼしかねません。このような課題を根本的に解決するには、分散したID情報を統合し、一元で管理できる基盤を整備する必要があります。
ID情報の一元管理は、セキュリティ強化に加え、コンプライアンス対応や運用負担の軽減にもつながります。しかし実際には、設計・導入に踏み切れない企業も多く、対応が後回しになっているのが現状です。その背景には、リソースの制約に加え、オンプレミス環境との整合性やクラウド移行に対する懸念、組織内の合意形成の難しさなど、さまざまな課題が挙げられます。
ID管理課題を放置すると起こる可能性のあるリスク

ID管理が適切に行われなかった場合、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。その結果、企業の信頼が損なわれたり、法的なトラブルにつながったりする可能性があるため、早めの対策が必要です。
不要なアカウントと過剰な権限が不正アクセスや情報漏洩を引き起こす
退職者のアカウントが削除されずに放置されていたり、異動後も以前のシステムにアクセスできる状態が続いていたりすることは、無視できないセキュリティリスクのひとつです。
例えば、退職者のIDが有効なままでは、外部からの不正アクセスや社内データが持ち出される危険性が高くなります。また、異動者が旧業務のシステムにアクセスできる状態が継続すれば、機密情報に触れるリスクも高まります。
たとえ内部の従業員であっても、過剰な権限を持っていることで、本来アクセスできない重要データに意図せずたどり着き、削除や改竄といったインシデントにつながる可能性も否定できません。 このように、不要なアカウントや権限を放置することは、システム全体の管理を複雑化させ、運用や監査時の負担増にも直結します。
属人化と手作業に依存した運用がID漏れ・対応遅延・業務停止を引き起こす
ID管理を特定の担当者の手作業に頼っている場合、運用がその従業員に依存しやすくなり、多様なリスクが生じます。
例えば、IDの発行・削除の手順が文書化されておらず、自動化もされていないケースでは、登録ミスや削除漏れが懸念されます。その結果として、情報漏洩のリスクが高まるほか、新入社員や異動者に必要な権限を付与できず、業務の開始が遅延するなどのトラブルにもなりかねません。
また、担当者が不在の際には処理が止まってしまうため、運用内容がブラックボックス化することも考えられます。ID管理の効率化や透明性を保つためには、手順の標準化と自動化に取り組み、属人化を解消することが大切です。
ルール・責任・記録が曖昧なID管理が統制不全と監査対応の破綻を招く
曖昧なID管理は、運用効率やセキュリティ、コンプライアンスの全てに悪影響を及ぼします。このような状況を放置していると、組織全体の統制がうまく機能せず、監査対応も困難になりがちです。
例えば、管理の方針や責任範囲が文書として明確に定められていない状況は、管理の実効性を低下させるほか、属人化の加速を引き起こします。オンプレミス環境とクラウド環境の境界線、あるいは、システムごとにID管理が分かれた状況は野良IDを生み出し、組織全体のID管理の統制を不可能にします。
アクセスログが取得されていなかったり、記録が不完全だったりすると、操作履歴を特定できません。そのため、監査時の指摘やインシデント発生時の調査、説明責任に対する適切な対応が困難になります。このような課題を解決するには、組織の統制を強化して監査や経営判断に対応できる体制をしっかりと整える必要があります。まずルールの明文化に取り組み、IDや権限を一元管理するための環境を早急に整備しましょう。
ID管理の“見えていない課題”を可視化するには?

一見、IDの発行や削除ができているようでも、運用ルールや責任の所在が不明確であれば、それは適切な管理とは言えません。
例えば、アクセス権限が業務内容に合わせて見直されていないケースや、定期的な権限レビューが行われていない場合、セキュリティリスクが高まる可能性があります。こうした見えていない課題を把握するには、アクセス状況の可視化や定期的な権限の棚卸が欠かせません。
こうした課題に体系的に向き合う企業も増えており、ID管理とその運用ルールを一体的に整備するアプローチとして、IGA(Identity Governance and Administration)への注目が高まっています。
IGAは、ID管理とガバナンスを一体的に考える仕組みであり、アクセス権限を最適な状態に保つことで、セキュリティリスクの低減やコンプライアンス対応の強化を実現します。
IGA導入の前段階として、まず現在の運用体制を整理・可視化し、自社の課題を明確にすることが重要です。CTCが提供するアセスメントサービスでは、現状分析や潜在課題の抽出とシステム化構想の策定をサポートしています。IT環境の複雑化や働き方の多様化が進む中で、IGAの導入は、ID管理の全体設計にまだ踏み切れていない企業にとって、有効な第一歩をもたらします。
なお、IGAについては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
関連記事:IGAとは? デジタルワークプレイスに必要な理由と導入メリットを解説
ID管理課題の整理と対処の第一歩としてアセスメントを活用する

ID管理が抱える課題は多岐にわたるため、優先度の高い課題を正しく見極めることは困難です。まず現在の状況を正確に把握するために、現状のシステムや運用の課題を見える化するアセスメントを実施しましょう。
なぜ今「アセスメント」が求められているのか
ID管理の重要性は理解しているものの、課題が点在しているため、何から着手すべきか判断できずに悩むケースは多くあります。特に、IT環境が複雑になるほど、社内だけで現状を整理・分析することが困難になり、対応の優先順位を誤るリスクもあります。このようなケースで効果的なのがアセスメントの活用です。外部の専門家の視点を取り入れることで、運用上の見落としや改善のヒントが明確に把握できるようになり、より適切な対策を講じられるようになります。
CTCのアセスメントサービスが課題の可視化と対策の道筋を提供
CTCのアセスメントサービスは、従業員向けのID管理に課題を抱えている企業を対象に、現状の可視化・課題の抽出・対策の優先順位付けを短期間で実施します。
例えば、システムごとにID情報を個別で管理している場合、監査や棚卸の際に多くの工数を必要とするため、見えないコストを生み出す可能性があります。IT部門や関連部門の貴重なリソースが大幅に消費されると、組織全体の生産性に深刻な影響を与えかねません。
CTCが提供するアセスメントサービスでは、ワークショップ形式やヒアリングを通じて、既存の環境を整理し、ID管理全体の構成やギャップを明らかにします。課題の背景にあるリスクや運用上の問題点を明確にした上で、対応方針やシステム化の構想についての検討をサポートすることに加え、製品選定や運用ルールの整備といった具体的なステップまで踏み込んだ提案を行います。
自社の方向性が決まっていなかったとしても、ゼロから柔軟に取り組める構成となっている点も注目すべきポイントです。アセスメントを実施することにより、短期間で効果的な成果が期待でき、ID管理の基盤づくりに最適なスタートを切ることができます。
アセスメントが導く「次のアクション」とは
ID管理や認証に関するアセスメントは、単に課題をリストアップするだけではありません。次に取るべき具体的なアクションを示す「改善ロードマップ」としての役割も果たします。独自の手法を用いて運用状況を見える化し、表面化している課題だけでなく、まだ顕在化していない潜在的なリスクまで丁寧に分析します。このような分析の実行により、IGAの導入や運用自動化など、次のステップへよりスムーズに移行することが可能です。
また、ヒアリングやワークショップを通して現状を正確に把握することで、企業ごとの目的や要件に合った運用設計が可能となり、最適なID管理/認証基盤の導入や運用体制の実現に近づきます。このようなアセスメントは、IT運用の高度化や効率化が求められる現代において、継続的な改善とビジネスの成長を支える重要な基盤となります。
まとめ

CTCのアセスメントサービスでは、複雑になりがちなID管理の課題を短期間で見える化し、システム化と運用対処策の検討を実施した上であるべき姿の構想策定を支援しています。まず、現状を整理して課題の洗い出しを行った上で対処策を検討し、運用の負担軽減や管理体制を見直したうえで、システム化することが重要です。属人化や権限の肥大化、不十分なログ管理など、見落とされがちなリスクに関しては、お客様のセキュリティ規定のご提供やトレンドのご紹介、ヒアリングでの議論を通じて明らかにし、具体的な改善点としてご提案します。ID管理の最適化を実現するために、まずはアセスメントで現状を把握し、実効性のある改善策を講じましょう。
- カテゴリ:
- デジタルビジネス全般