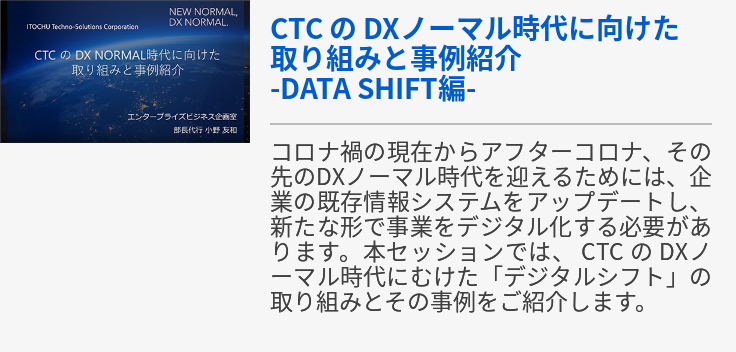2021年8月に公開された「DXレポート2.1」では、日本企業のDXを阻害している構造的な問題について、前身である「DXレポート2」よりも深く具体的に考察されるとともに、DXの先に目指すべき産業構造などが構想されています。本記事では、この「DXレポート2.1」の内容について包括的に解説していきます。
DXレポート2.1の概要
「DXレポート2.1」とは、2018年に経済産業省が公開した初代の「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」、そして2020年の「DXレポート2(中間取りまとめ)」に続く、3本目の「DXレポート」です。「DXレポート2.1」は2021年8月に公開されたもので、内容としては「DXレポート2」の補完編に当たります。
「DXレポート」においては、「2025年の崖」という象徴的な言葉を用いて、日本企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む必要性が強調されました。そして「DXレポート2」では、DXを実現するためには「レガシー企業文化からの脱却」や「ベンダー企業とユーザー企業の共創関係の構築」が重要であると指摘しています。これらに続く「DXレポート2.1」では、そこからさらに進んで、ベンダー企業とユーザー企業の悪い意味での相互依存関係を断ち切り、産業構造から変革していく必要性が説かれています。
ユーザー企業とベンダー企業の相互依存
「DXレポート2.1」で指摘されているユーザー企業とベンダー企業の相互依存とは、一体どのような関係を指しているのでしょうか。
まず「DXレポート2.1」においては、デジタル社会の理想像として、ベンダー企業とユーザー企業が垣根をなくし、それぞれの企業が互いにデジタル・ケイバビリティを磨く中で、新たな価値創出や成長を実現していく姿を想定しています。その理想像に対して現状は、「下請けとしてスキルやノウハウを提供するベンダー企業」と「ベンダー企業の支援を受けてDXを推進するユーザー企業」というように、両者のあいだには明確な線引きがなされており、しかも両者のあいだには悪い意味での相互依存関係(「低位安定」の関係)が築かれていると指摘されています。
というのも、「DXレポート2.1」によれば、既存のIT産業における業界構造は、ユーザー企業は「コストの削減」を委託に求め、ベンダー企業は「低リスクかつ長期安定のビジネス」を受託に求めることで成り立っているとされています。この関係は一見すると何の問題もないように思えますが、実際には下記のように、ユーザー企業とベンダー企業の双方にとってよい結果を生まない、負のスパイラルに発展する可能性があるのです。
ユーザー企業
この負のスパイラル構造において、ユーザー企業はITへの投資を避けるべきコストとみなしています。したがって、ユーザー企業はITベンダーに価格競争をさせ、より安いところに委託することでコストを削減しています。
そして、その導入・運用については、ベンダー企業に任せきりにしてしまうため、ユーザー企業内部にはITへの対応能力が蓄積されず、ITシステムのブラックボックス化や、ベンダーの固定による経営のアジリティ低下などにつながります。その結果、最終的には顧客のニーズに応えるための価値提案能力までも衰えてしまい、デジタル社会の敗者となってしまうのです。
ベンダー企業
他方、ベンダー企業においても、低コストを売りにしたビジネスモデルには弊害があります。低コスト・低リスクのビジネスは、成果ではなく労働量を値付けすることで成り立つものです。しかし、こうしたビジネスは利益水準の低下による多重下請け構造を生み、売上総量の確保が必要になります。
そして、売上総量(≒労働量)を確保するために、生産性を向上させるようなインセンティブを出しにくくなります。最終的には、売上率の低さから技術開発に必要な投資をする経済的余裕も失っていき、本来の使命である「デジタルの提案」ができなくなってしまうのです。結果、ベンダー企業もユーザー企業と同じく、デジタル社会の敗者となってしまうことが想定されます。
「DXレポート2.1」においては、このようなユーザー・ベンダー間の悪しき相互依存関係が、DXを阻害する構造的な要因として働いていると考えられているのです。ユーザー企業にしても、ベンダー企業にしても、デジタル競争を中長期的に勝ち抜いていくためには、自社がこのような負のスパイラルに陥っていないか自省し、必要であればそこから脱却する方途を自ら探らねばなりません。
デジタル産業の企業への変革を阻む3つのジレンマ
「DXレポート2.1」においては、デジタル産業の企業への変革を阻む要素として、上述の相互依存関係に加えて、以下3つのジレンマの存在を指摘しています。
- 危機感のジレンマ
- 人材育成のジレンマ
- ビジネスのジレンマ
ここでは、それぞれのジレンマの内容を解説していきます。
危機感のジレンマ
「危機感のジレンマ」とは、変革に必要な経済的余裕があるうちは、変革に対する危機感が足りず、危機感が高まったころには業績不振により、変革するに足りる企業体力を失っている状態を指します。目先の成功に惑わされず、将来を見据えた施策を取り続ける必要性を的確に示した表現です。
人材育成のジレンマ
「人材育成のジレンマ」には、現在のIT人材不足の本質が鮮明に表されています。日進月歩で進化するICTは、技術が陳腐化するのも非常に速く、時間を費やして習得しても、その頃にはすでに古い技術となっていることが懸念されます。
もちろん、中には素早く新技術に適応できる人材もいますが、そうした優秀な人材ほどすぐに他社へ引き抜かれてしまうのが実情です。かといって、人材育成を最初から諦めてしまえば、現在の需要過多な状況下でIT人材を充足することは叶いません。DXを推進するためには、IT人材の確保が必須となりますが、その人材確保における労苦を表現したのが「人材育成のジレンマ」です。
ビジネスのジレンマ
上記2つのジレンマは、ベンダー企業・ユーザー企業双方が共有するジレンマですが、3つ目の「ビジネスのジレンマ」はベンダー企業固有の問題です。前章の「ユーザー企業とベンダー企業の相互依存」でも指摘したように、現在のベンダー企業はユーザー企業からの受託によってビジネスを成立させています。その一方、DXの理想としては、ユーザー企業がベンダー企業に頼りきりにならず、対等な立場で(あるいは、そもそもユーザー企業・ベンダー企業という境界すらなくして)DXを実行していくことが望ましいとされます。つまり、ユーザー企業そのものがデジタル企業に生まれ変わるのです。
ユーザー企業が自らシステムを内製できるデジタル産業に変貌してしまえば、ベンダー企業はそれまで委託していた自分たちの仕事がなくなってしまい、売上規模が縮小してしまいます。ベンダー企業に求められている役割には、ユーザー企業のDX支援ももちろん含まれていますが、その成功が自分たちの首を絞めることにもつながってしまうのです。これはベンダー企業にとって、非常に悩ましいジレンマです。
「DXレポート2.1」では、こうしたジレンマを突破するには、経営者のビジョンとコミットメントが必須であると指摘されています。また、技術がそのうち陳腐化するとしても、ベンダー企業がそれまで蓄え続けてきた技術が、ただちに不要になるわけではありません。ベンダー企業がこれからのDX時代においても必要な存在であり続けるためには、最新の技術を追い続ける飽くなき姿勢こそが求められるのです。
デジタル社会とデジタル産業の姿
「DXレポート2.1」においてカギとなる概念として、「デジタル社会」と「デジタル産業」が挙げられます。以下では、「DXレポート2.1」に記載されている、それぞれの概念の特徴を解説していきます。
デジタル社会の特徴とは
まず、デジタル社会の特徴として、「DXレポート2.1」では次の4つの要素が示されています。
- 様々なプロセスにおいて、人による主観的な判断は、データに基づく客観的な判断へと変化する
- クラウドサービスとして価値が提供され、環境の変化に伴ってサービスが常にアップデートされる
- インターネットを介して、サービスが世界規模でスケールする
- サービスがオープンなアーキテクチャのもとで相互に接続する。企業は、この相互接続を用いて他社のバリューチェーンに参画したり、他社のサービスを活用して価値を創出したりする。
このデジタル社会においては、価値創出の源泉は現実空間からサイバー空間に移行し、その空間にてさまざまな企業や組織が協力して、社会的課題の解決や新たな価値創出に取り組みます。こうした理想のデジタル社会では、グローバル的に活躍する企業や、カーボンニュートラルなどのSDGsに貢献する企業も出てくるかもしれません。
また、昨今では新型コロナウイルスの影響によって、場所を問わずに働けるリモートワークが普及しましたが、理想のデジタル社会においては企業自身も地方・都会の区別なく、あるいは資本の大小すら関係なく、新たな価値創出に参画できるようになることが重要とされています。
デジタル産業とは
上記のようなデジタル社会を実現するうえで、中心的な役割を果たすのがデジタル産業です。「DXレポート2.1」において、デジタル産業の特徴は主に以下の5要素に集約されています。
- 課題解決や新たな価値・顧客体験をサービスとして提供する
- 大量のデータを活用して社会・個人の課題を発見し、リアルタイムに価値提供する
- インターネットに繫がってサービスを世界規模でスケールする
- 顧客や他社と相互につながったネットワーク上で価値を提供することで、サービスを環境の変化に伴って常にアップデートし続ける
- データとデジタル技術を活用し、マルチサイドプラットフォームなどのこれまで実現できなかったビジネスモデルを実現する
デジタル産業の構成企業は、価値創出の手段を「ビジネスケイパビリティ」から「デジタルケイパビリティ」へと移行し、それらを通して他社・顧客とともにエコシステムを築いていきます。
ピラミッド構造からネットワーク構造へ
従来の産業とデジタル産業を隔てる大きな違いが、ピラミッド型からネットワーク型へとビジネス構造が変化することです。ICTの発展は、Webやスマホアプリなど、従来と比べて遥かに多くの顧客接点を企業にもたらしました。現代の企業は、それらの顧客接点から得たデータに基づいて顧客ニーズを分析し、迅速に市場に対応する必要に迫られています。また、顧客へ価値を迅速に届けるには、自社だけですべてをまかなうのではなく、業種・業界の別なく他社のサービスと組み合わせるなどして、柔軟な対応を取ることが重要です。
このように、市場との対話を通して柔軟な対応を取っていくには、従来の大企業を頂点としたピラミッド型(多重下請け型)のビジネス構造は硬直的すぎます。そこで重要となるのが、市場ニーズを覆うように個々の企業がバリューチェーンを構成し、状況に応じて柔軟に連携し合うネットワーク型のビジネス構造です。デジタル産業において取引の指標は、労働量ではなく「価値」に重点が置かれます。そして企業間のネットワークは、顧客価値に対するビジョンや共感によってつながっていくのです。
ユーザー・ベンダーの関係から脱却した先の企業の姿
「DXレポート2.1」において、既存のユーザー・ベンダー関係から脱却したデジタル産業の構成企業は4つに類型化できるとされています。以下では、それぞれの企業類型の特徴を解説していきます。
類型1. 企業の変革を共に推進するパートナー
類型1は、ビジネスモデルや組織構造の変革などを目指す企業の「伴走支援」をする企業です。従来のユーザー・ベンダー関係においては、ユーザー企業が自社での内製を避けるために、開発をいわば「バトンタッチ」するのが通例でした。しかし、この新しい類型の企業は顧客企業に歩み寄り、ともに新しいビジネスモデルを構築し、そこで得られた知見や技術を共有するパートナーとして活動します。
類型2. DXに必要な技術を提供するパートナー
類型2は、DXのために特定技術の獲得を必要としている企業に、伴走支援をする企業です。この企業は、一流技術者が最新のIT技術や特定領域の深い知識、ノウハウなどを顧客企業に提供し、デジタルの方向性やDXに必要な諸技術の組み合わせを決定する際などに役立てます。
類型3. 共通プラットフォームの提供主体
類型3は、デジタル産業のネットワークを構成するうえで重要な、共通プラットフォームを提供する企業です。この企業は、業界ごと、あるいは業界を横断した協調が成立するための基盤を構築し、類型1や類型2の企業を含んだエコシステムをサービスとして提供します。
類型4. 新ビジネス・サービスの提供主体
類型4は、類型1・2・3の企業と協調しながら、新しいビジネスを市場に提供する企業です。この企業は類型3のプラットフォームを活用することで、スケーラブルで持続性の高いサービスを開発し、市場に新しい価値を届けます。
日本が今後進めていく取り組み
最後に、「DXレポート2.1」において指摘されている、日本が今後進めていくべき取り組みについて解説します。
デジタル産業指標(仮)の策定
第一に必要なのが、「デジタル産業指標」の策定です。これは、先述したデジタル産業の構成企業の4類型それぞれに関する指標を意味しています。4類型それぞれの概略についてはすでに解説しましたが、「自社はどの類型に分類されるか」「その企業類型における自社の成熟度はどれほどか」を判断するには、定量的な評価指標が欠かせません。デジタル産業指標の策定は、そのために必要な取り組みです。
DX成功パターンの策定
次に必要なのが、「DX成功パターン」の策定です。日本企業のDXが思うように進んでいない現状は、「DXレポート2」の時点ですでに明らかにされています。今後の日本において、より一層DXへの取り組みを加速させ成功に導くためには、企業がDXの際に手がかりとできるロードマップをさらに整備していくことが必要です。
DX成功パターンの策定においては、「DXレポート2.1」で説明されたデジタル産業を目指すべき方向として、そこに至るまでの企業変革の道筋を抽象的なパターンとして描き出すことを目的にします。
まとめ
2020年に公開された「DXレポート2」では、日本企業におけるDXが思うように進んでいない現状が指摘されていました。本記事で解説した「DXレポート2.1」では、その原因の一端として、ユーザー・ベンダー間の関係の構造的問題が挙げられ、さらに深い考察がなされています。また、「DXレポート2.1」の特筆すべき点としては、DXの先に実現される社会や産業のあり方を、デジタル社会・デジタル産業の説明を通して描いたことが挙げられるでしょう。
本記事でご紹介した「DXレポート2.1」や、その他の資料が示すように、経済産業省はDXの推進を日本の国策事業とみなして注力しています。今後もDXの指針を示す経産省の動きには注視していくことが重要です。
- カテゴリ:
- デジタルビジネス全般