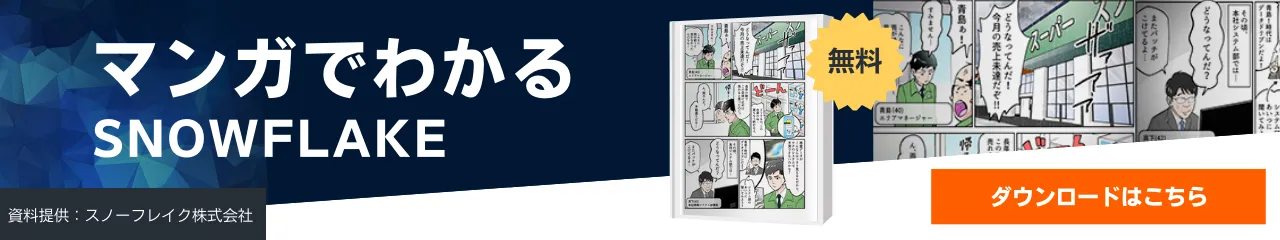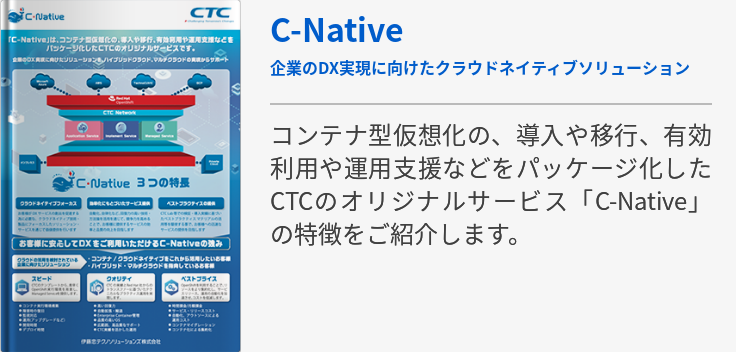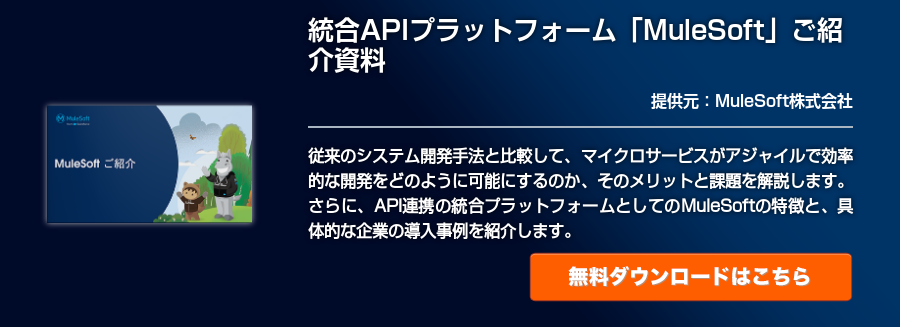非代替性トークン(NFT)は、ブロックチェーン技術を基盤としたデジタル資産です。NFTは同じような見た目のデジタルデータであっても、記録された識別情報によってその唯一性が認められており、デジタルアートや音楽など、多様な形での利用が拡大しています。本記事では、NFTの仕組みや特性、今後の課題について詳しく解説します。

非代替性トークン(NFT)とは?
非代替性トークン(ひだいたいせいトークン)は、NFT(Non-Fungible Token)として一般的に知られています。このテクノロジーは、ブロックチェーンをベースとして構築されている、代替不可能なデジタルのデータを指します。
そもそもトークンとは
トークン(Token)は、プログラミング言語において、プログラミングコード上で意味を持つ最小単位の文字の並びであり、直訳すると「しるし・証拠」という意味になります。この概念は、近年、ブロックチェーン技術や仮想通貨、NFTなどの暗号資産にも拡張されています。トークンの価値は、特定の代表者が決めるというものではなく、利用者が価値を相互に信頼し合いながら形成されていきます。
暗号資産との違い
暗号資産とトークンは、似た技術として捉えられることもありますが、実際には異なった性質を持っています。その最も顕著な違いは、トークンが代替可能か、という点にあります。
暗号資産は、代替性トークン(FT:Fungible-Token)として知られていますが、これは各トークンが同価値であり、他の同じ種類のトークンと交換できることを意味します。例えば、1ビットコインは別の1ビットコインと同価値であり、交換可能です。通貨や株式のような資産と同じような代替性を持っています。
非代替性トークン(NFT)でできること
非代替性トークンは、ブロックチェーンの技術を活用し、デジタル資産に一意性と所有権を付与する革新的な手段です。この一意性は、デジタルの世界において、アートや写真集、トレーディングカード、ファッション、音楽など、多くの分野で新たな価値を生み出しています。
デジタルアートにおいては、NFTが証明する「1点ものであることの価値」によって、実際に数億円という驚異的な価格で取引される作品も存在します。また、デジタルトレーディングカードでは、特定の瞬間やプレイを捉えた動画がカードとして取引され、その希少性によって価格が変動します。
仮想空間では、土地取引も行われており、仮想不動産とも呼ばれています。仮想空間内での土地は、ゲームやコミュニティ活動の場として、または広告スペースとして利用されることが多くあります。
NFTが注目された背景
NFTは、2021年頃から急速に注目を集めるようになりました。Twitterの創始者であるジャック・ドーシー氏が、自身の初ツイートをNFTとして出品し、それが約3億円で売却されたことは、多くの人々に衝撃を与えました。さらに、テスラとスペースXのCEOであるイーロン・マスクが、デジタルミュージックをNFTとしてオークションにサイトに出品すると、1億円を越える入札が行われました。
これらの出来事は、NFTが単なるデジタルデータ以上の概念として認識されるようになった一例であり、資産価値が認められ、市場が形成されたことを象徴しています。従来、デジタルデータはコピーが容易にできるため、資産価値を認めるのが難しいという欠点がありました。しかし、NFTはブロックチェーン技術を用いて、デジタルデータに一意性と所有権を確立できます。
非代替性トークン(NFT)の仕組み・特徴
非代替性トークンはブロックチェーン技術を活用し、デジタルデータに一意の価値を付与する新しい形態のデジタル資産です。この独自性と所有権の証明能力により、NFTはデジタルアートから音楽、仮想土地まで多様な用途で利用されています。NFTの基本的な仕組みと多面的な特性について詳しく解説します。
1. 代替不可能性(唯一無二)
NFTは、デジタルアセットの新しい形態として注目を集めていますが、その最大の特徴は代替不可能性、すなわち唯一無二であることです。
例えば、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は、同じ通貨単位であれば互いに代替可能です。しかし、NFTは同じ見た目のデジタルアートであっても、ブロックチェーンに記録されている独自の識別情報によってその価値が決まります。
この代替不可能性は、オリジナルとコピーを明確に区別する力を持っています。一般的なデジタルファイルとは異なり、NFTはブロックチェーン技術によってそのオリジナリティが保証されています。例えば、NFTのアート作品をスクリーンショットで保存することは可能ですが、そのスクリーンショットはブロックチェーンに紐づけられている情報を持っていないため、オリジナルではないと判別されます。
2. プログラマビリティ
プログラマビリティは、NFTの魅力的な側面の一つで、NFTに情報や機能を加えることが可能です。この機能により、NFTには単なるデジタルアートや収集品以上の価値が生まれます。NFTは単なる「所有権の証明」から一歩進んで、多様な用途で活用できるようになります。
例えば、二次流通の際に売上の一部が元の作者に戻るような仕組みをNFTに組み込めます。これは、アーティストやクリエイターにとって非常に魅力的な機能です。従来、このような取り決めを行うには、著作権管理団体を通す必要がありました。しかし、NFTのプログラマビリティを利用することで、従来のような第三者機関を介さずに直接取引が可能になります。
3. データの改竄が困難
NFTの重要な特性として、データの改竄が極めて困難である点が挙げられます。NFTのベースであるブロックチェーンはデータを分散して管理する仕組みであり、1つのデータを改竄しようとする場合、ブロックチェーン上に点在する全ての場所で同時に改竄を行わなければなりません。
この特性がもたらすセキュリティ性の高さは、NFTが多くの用途で活用される大きな理由です。例えば、デジタルアートやコレクタブル、さらには重要な契約書まで、NFTとして発行することでその真正性を保証できます。
4. 取引可能性
取引可能性もNFTの魅力の1つです。NFTは非中央集権的なブロックチェーン上で管理されているため、暗号資産と同じように自由に移転や取引が可能です。この特性は、NFTが多様な用途で活用される背景にもなっています。
暗号資産の取引と同様に、主に取引所やマーケットプレイスなどで売買されます。これにより、ユーザーは自分が所有するNFTを簡単に他のユーザーに売却したり、逆に購入できたりします。また、非中央集権的な性質により、第三者の介入なく、直接取引が行える場合もあります。これは、従来のアート作品やコレクタブルなどが売買される際に必要だったオークションハウスやギャラリーなどの中間業者を排除し、より効率的な取引を可能にしています。
5. 相互運用性
NFTのもう一つの注目すべき特性は、その相互運用性(Interoperability)です。この特性は、NFTが多様なプラットフォームやサービスで容易に取り扱われることを意味します。その背景には、NFTの仕様が共通規格に基づいている点があります。一般的には、イーサリアムのERC721という規格が広く採用されています。
この共通規格により、デジタルアート、写真、音楽など、異なる種類のデジタル資産でもその鑑定書の書式が同一です。これは、例えばあるプラットフォームで購入したNFTを、別のプラットフォームでも問題なく取り扱えるという利点につながります。規格を逸脱しない限り、どのサービス上でもそのNFTは有効であり、その価値と真正性は保証されます。
非代替性トークン(NFT)の今後の課題
非代替性トークンが多くの注目を集める一方で、今後の課題は少なくありません。特に日本国内においては、法整備がまだ十分に進んでいないのが現状です。事業者が遵守すべき法規制が未整備であるため、NFT関連のビジネスを展開する際には、多くの不確実性が存在します。
2023年1月13日には、国税庁がNFTの税務上の取扱いについて公表しました。しかし、それでもまだ多くの課題が残されています。税務だけでなく、著作権や契約法、消費者保護など、多角的な法整備が必要です。
日本国政府はWEB3.0を推進する方針を明確にしており、NFTに関する施策の検討も進めているとされています。今後法整備が進展する可能性も高く、その動きには多くの関心が寄せられています。
国税庁|NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年1月13日)
まとめ
非代替性トークンとは、代替不可能で唯一無二の価値が認められるトークンであり、暗号資産などと同じブロックチェーン技術を基盤にしています。非代替性トークンの性質を用いることで、デジタルデータに資産価値を与えられるようになり、2021年から始まるNFTブームを呼び起こしました。日本国内での法整備がまだ追いついていないという課題がありつつも、今後の非代替性トークンの発展が注目されます。
- カテゴリ:
- データマネジメント